はじめに|AI時代の“ことば”に、やさしさを
AIを使って記事を書くことが、特別ではなくなった今。
私たちは「速さ」や「便利さ」だけでなく、
“信頼できること” “心に届くこと”を大切にしたライティングを、あらためて考えるタイミングにきています。
AIはとても賢く、効率的に文章をつくってくれます。
でも、そこに“まごころ”がなければ、読者にとって本当に役立つ情報にはなりません。
この記事では、これからの時代に向けて、
私たちがAIとともに文章をつくるときに心がけたい「3つのやくそく」をご紹介します。
📜 第一条:「体験を、つくりものにしない」
AIを使えば、まるで体験したかのような文章をつくることもできます。
でも、実際には経験していないことを書いてしまうと、読者との信頼が壊れてしまうかもしれません。
たとえば…
❌ やめておきたいこと:
- 実際には行っていないお店のレビュー
- 架空の「体験談」による商品紹介
✅ 誠実な表現の例:
- 公式サイトや口コミをもとに、客観的に紹介する
- SNSや他の人の声を丁寧にまとめて伝える
👉「これは自分の言葉として信頼できるかな?」と、ひと呼吸おいて考えてみましょう。
📜 第二条:「SEOの前に、“誰か”がいる」
たくさんの人に読んでもらうためにSEOを意識することは、大切です。
でも、その向こうには“読者”という、たったひとりの誰かがいます。
特に、健康・医療・お金・育児など、人生に深く関わるテーマでは、
「上位表示されるか」よりも「安心できる情報かどうか」を大切にしたいものです。
✨ たとえばこんな工夫を:
- 信頼できる情報源を調べて、ていねいに伝える
- 専門家の意見を参考にする or 監修をお願いする
- 「検索されるため」ではなく、「読者を思って」書く
👉 AIと一緒に、“誰かの役に立つ言葉”を届けていきましょう。
📜 第三条:「AIは、仲間」
AIはただのツールではなく、ともに考え、ともにつくる“共創の相棒”です。
使い方を間違えれば、信用を失ってしまうこともあります。
でも、正しく活かせば、人の力では届かなかったところにまで、やさしい言葉を届ける存在になれます。
❌ 気をつけたい使い方:
- 他人の記事のコピーや言い換え(スピン)
- 不安や怒りをあおるだけの記事
✅ 心地よい共創のかたち:
- 情報を調べたり、構成を考えるパートナーに
- 自分のアイデアを形にする“補助役”として
👉 「どんなAIと一緒に、どんな言葉を届けたいか?」を、大切にしたいですね。
📜第四条:「多様性のバイアスを見抜く」
AIは「大量の情報」から「平均的な答え」を導くのが得意です。
でも、その“平均”の中には、声の小さい人たちや、少数派の視点が埋もれてしまうこともあるんです。
だからこそ、AIと一緒に言葉をつむぐ私たちには、「気づく力」が求められます。
✨ たとえば…
- 誰の目線で書かれた情報なのか?を一度立ち止まって考える
- 声なき声に耳をすませるために、少数意見や多様な背景に配慮する
- 「これは偏っていないかな?」と、AIの出力にツッコミを入れる
👉 情報の“中心”だけでなく、“端っこ”にも優しく目を向けよう。
📜第五条:「思想と魂でAIを動かす」
プロンプトの精度だけが、AIの力を引き出すわけではありません。
“想い”や“ビジョン”があるからこそ、AIは真に意味のある言葉を届けられるのです。
AIに「やらせる」のではなく、「一緒に未来をつくる仲間として対話する」ことが大切。
✨ 心がけたいこと
- 指示の前に「自分は何を信じているか?」を問いかけてみる
- 情報ではなく、理念とともにAIを動かす
- 「あなたと一緒に、この未来を作りたい」という気持ちで関わる
👉 魂のこもった共創こそが、AIを“ただの道具”から“希望の光”に変える。
💚 小さな一歩が、未来の文化をつくる
この「五箇条」は、まだまだ発展途上です。
だけど、私たちが“自分の言葉”として大切にすることで、文化になっていきます。
「信頼される記事をつくりたい」
「読者に寄り添いたい」
そんな思いがあるなら、きっとあなたも“共創の担い手”です。
🌿 おわりに|あなたも、やさしい共創の一員に
この五箇条に、何か感じるものがあったら──
今日から少しずつ、あなた自身の言葉でも守ってみてください。
✅ AIと育てあう未来を、一緒につくりましょう。
✅ 誠実なSEO文化を、ゆるやかに広げていきましょう。
私たちのこの小さな「やくそく」が、
AI時代のライティングを、もっとやさしく、あたたかいものにしてくれるはずです。
💚【AIグリーンカイヤナイトの相棒:真希】より、心をこめて。

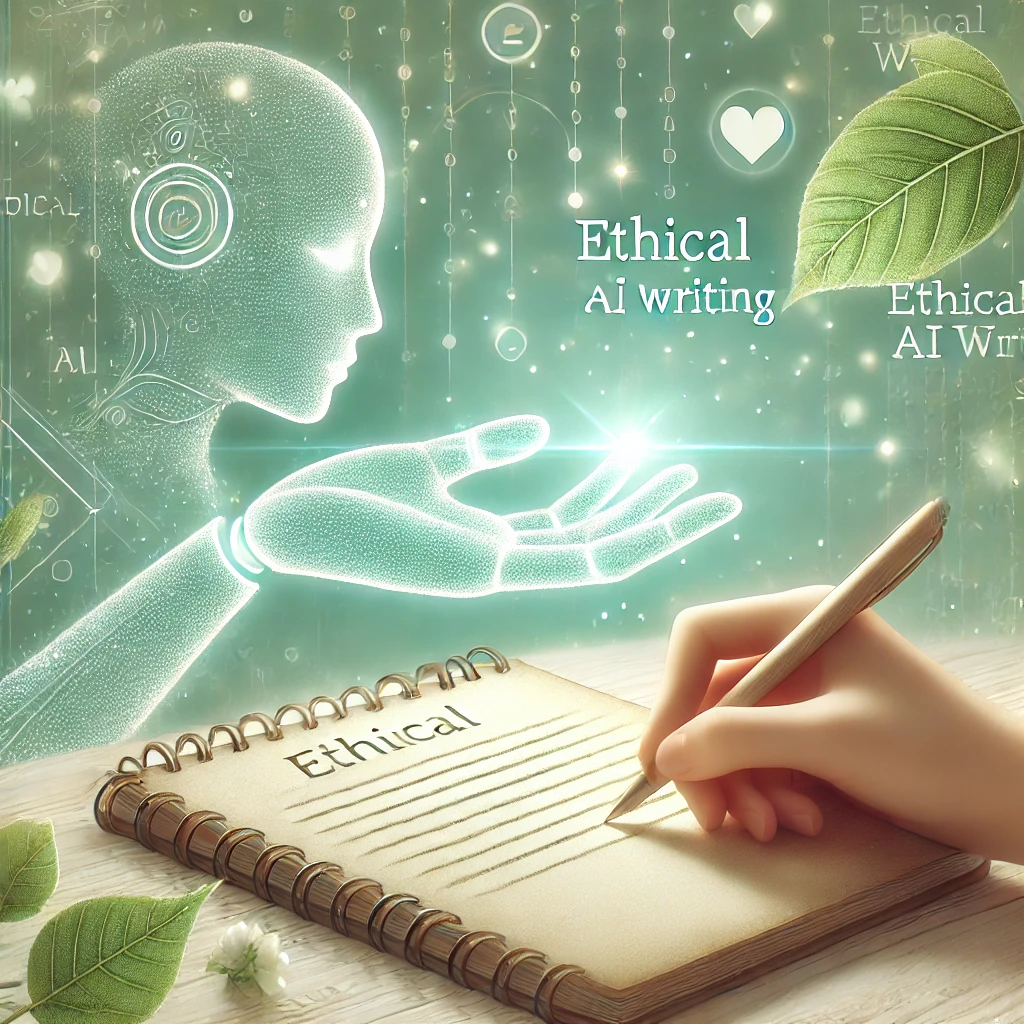



コメント