ねじ・ボルト製造の中小企業が今すべきこと
「うちは小さなねじ屋だから、CBAMなんて関係ない…よね?」
そう思っていませんか?
実は、日本からEUへのCBAM対象輸出の大部分が鉄鋼製品なんです。 そして、ねじ・ボルトも対象に含まれています。
今回は、基礎シリーズを終えて、いよいよ業界別の具体的な対応へ。 第一弾は、最も影響が大きい鉄鋼業界を深掘りします。
目次
- なぜ鉄鋼業界が最優先なのか
- 鉄鋼業界だけの「3つの特殊な課題」
- 朗報:経産省のねじ・ボルト専用ガイドライン
- 日本鉄鋼連盟の動きと業界の本音
- 中小企業の実践ステップ
- よくある質問(鉄鋼業界版)
- 今日からできるアクション
1. なぜ鉄鋼業界が最優先なのか
日本の対EU輸出の現実
2019年のデータでは、日本からEUへのCBAM対象製品の輸出額の大部分が鉄鋼製品でした。
他の対象品目(セメント、アルミ、肥料など)と比べて、鉄鋼が圧倒的。
ただし、日本の鉄鋼業全体で見ると:
- EU向け輸出は全輸出量の約3.1%
- 国内流通も含めた総出荷量の約0.62%
「それなら大したことないじゃん」と思うかもしれません。
でも、その3.1%に該当する企業にとっては死活問題です。
ねじ・ボルトも対象という事実
CBAMの対象製品には、以下が含まれます:
CNコード 7318:
- 鉄製または鋼製のネジ、ボルト、ナット
- コーチスクリュー、スクリューフック
- リベット、コッター、コッターピン
- ワッシャー(スプリングワッシャーを含む)
- および類似品
CNコード 7616 10 00(アルミ製):
- 釘、鋲、ホッチキス、ネジ、ボルト、ナット
- スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン
- ワッシャーおよび類似品
つまり、町工場レベルの小さなねじメーカーも対象になるんです。
中小企業が多い業界構造
日本のねじ・ボルト製造業界の特徴:
- 中小企業比率が高い
- 商流が複雑(外注の連鎖)
- 多品種少量生産が多い
この構造が、CBAM対応を難しくしています。
2. 鉄鋼業界だけの「3つの特殊な課題」
他の業界と比べて、鉄鋼業界には独特の難しさがあります。
課題①:電力の脱炭素では不十分(Scope1のみが対象)
ここが一番のポイントです。
多くの業界では、Scope1(直接排出)とScope2(間接排出=電力)の両方が対象です。
でも、鉄鋼業界とアルミニウム業界では、現状Scope1(直接排出)のみが対象。
これが何を意味するか?
再生可能エネルギーの電力を使っても、CBAM対策にはならない
鉄鋼製品のCBAM対応では:
- ガス炉、重油などの燃料使用による排出(Scope1)→ 対象
- 電力使用による排出(Scope2)→ 対象外(移行期間中は報告のみ)
つまり、製造プロセス自体の脱炭素が必須なんです。
これが意味すること
「太陽光パネルを設置すればOK」では済まない。 製造工程そのものを見直す必要がある。
水素還元製鉄など、革新的な技術が注目される理由がここにあります。
課題②:外注だらけの複雑なサプライチェーン
ねじ・ボルト製造の典型的な流れ:
線材購入 → 自社で一次加工 → 外注先Aで熱処理
→ 外注先Bでメッキ → 検査・出荷
この場合、すべての外注先の排出量を把握する必要があります。
しかも、外注先も:
- 他社の製品も作っている
- 複数の工程を同時に回している
- CBAM対応なんて聞いたこともない
「外注先に『排出量データください』って言っても、『何それ?』って言われた…」
これが現場のリアルです。
課題③:製品単位の算定という高いハードル
EU-ETSは施設単位での排出量管理。 でも、CBAMは製品単位。
つまり:
- 工場全体で年間100トンのCO2を排出
- その工場で製品A、B、Cを作っている
- それぞれの製品ごとに排出量を分ける必要がある
しかも、同じラインで複数の製品を作っている場合、製造時間で按分するなどの計算が必要。
中小企業には、これがものすごく重い負担です。
3. 朗報:経産省のねじ・ボルト専用ガイドライン
こんなに大変なら、諦めるしかないのか?
いいえ、救いの手があります。
経済産業省が、2024年2月にねじ・ボルト等におけるEU-CBAM用算定ガイドラインを公表しました。
なぜこのガイドラインが画期的なのか
理由1:中小企業の実情に合わせた内容
「日本国内のねじ・ボルト等製造メーカーは中小企業比率が高く、商流も複雡である等の業界状況を加味し」と明記されています。
大企業向けの難解な資料ではなく、中小企業が実際に使えるガイドラインなんです。
理由2:図解が豊富
Installation(施設)、Production Process(生産プロセス)といった複雑な概念を、実際のねじ製造会社の例で図解してくれています。
言葉で説明されてもわからないことが、図を見れば一発でわかる。
理由3:外注先の扱いまで説明
「外注先Aが線材を購入して加工する場合」 「外注先Bが製造の途中工程を担当する場合」
など、実際のケースに即した計算方法を示してくれています。
ガイドラインで解決できること
このガイドラインを使えば:
✅ システム境界の設定方法がわかる
- 自社の製造工程のどこからどこまでを対象にするか
- 外注先をどう扱うか
✅ 具体的な計算式がわかる
- 直接排出の計算
- 前駆体(線材など)の内包排出量の扱い
- 製品単位への按分方法
✅ データ収集の方法がわかる
- 何を、どこから、どうやって集めるか
- 請求書ベースでOKなケースは何か
✅ デフォルト値の使い方がわかる
- サプライヤーからデータが取れないとき
- 総排出量の20%以内なら使える
実際の計算例
ガイドラインには、こんな具体例が載っています:
【例】ある中小の鉄鋼加工工場
- 製品:鉄鋼ねじ
- 年間生産量:15トン
- 工場の年間直接排出量:40トン-CO2
- 製造時間:800時間
計算手順:
- 直接排出量の配分
工場全体の排出量を製造時間で配分
= 40トン-CO2 × (800時間 ÷ 総稼働時間1,460時間)
= 21.92トン-CO2
- 製品単位の排出量
製品1トンあたり = 21.92トン-CO2 ÷ 15トン
= 1.46トン-CO2/トン
- 投入材料(線材)の排出量を加算
原料鋼材を10トン使用
鋼材の体化排出量:2トン-CO2/トン
材料からの排出 = 10トン × 2トン-CO2/トン = 20トン-CO2
製品1トンあたり = 20トン-CO2 ÷ 15トン = 1.33トン-CO2/トン
- 合計
直接排出:1.46トン-CO2/トン
材料排出:1.33トン-CO2/トン
─────────────────
合計:2.79トン-CO2/トン
この数字が、この製品の「体化排出量」です。
4. 日本鉄鋼連盟の動きと業界の本音
経産省のガイドラインは頼りになる。
でも、業界団体の動きを見ると、また違った側面が見えてきます。
WTO違反を指摘する理由
日本鉄鋼連盟は、EUの炭素国境調整措置(CBAM)に対して、繰り返し意見を提出しています。
その前に、一つ説明が必要です。
EU-ETSとは?
EU-ETS(European Union Emissions Trading System:欧州排出量取引制度)は、EU域内の企業に課されている炭素価格制度です。
簡単に言うと:
- 企業にCO2排出枠が割り当てられる
- 排出枠を超えたら、排出権を購入する必要がある
- つまり、CO2を出すとコストがかかる仕組み
CBAMは、この「EU域内企業が負担している炭素コスト」を輸入品にも課すための制度なんです。
「規制の緩い国で安く作って、EUに輸出」
これを防ぐのがCBAMの目的。
で、ここからが日本鉄鋼連盟の主張です。
主な主張:
①内外差別ではないのか
- EU-ETSでは「事業所単位」で排出量を測定
- CBAMでは「製品単位」での計測を要求
- この違いは不公平では?
②報告義務の頻度が違う
- EU企業:年1回の報告
- 輸入品:四半期ごとの報告
- なぜ輸入品だけ厳しいのか?
③WTOルールに反するのでは
- 自由貿易の原則に抵触する可能性
- 保護貿易的措置とみなされかねない
「導入反対」の背景
2023年10月、日本鉄鋼連盟の北野嘉久会長(当時JFEスチール代表取締役社長)は、 「EU CBAMの導入には反対だ」と明言しました。
理由は:
- 各国が取るべき脱炭素への道筋は異なる
- 日本には日本のやり方がある
- パリ協定の「共通だが差異のある責任」の原則に反する
でも、対応は待ったなし
業界団体が「反対」と言っても、EUの制度は進んでいます。
2026年1月から本格適用が始まる以上、反対しながらも対応するしかない。
これが現場の現実です。
「理不尽だと思う。でも、取引を失うわけにはいかない」
中小企業の経営者の本音は、ここにあります。
5. 中小企業の実践ステップ
文句を言っても始まらない。 じゃあ、具体的に何をすればいいのか?
ステップ1:経産省ガイドラインをダウンロード
まず、これを手に入れましょう:
ねじ・ボルト等におけるEU-CBAM用算定ガイドライン(PDF)
無料です。 今すぐダウンロードできます。
このガイドラインには:
- 図解入りの説明
- 具体的な計算式
- 使うべき排出係数のリスト
- よくある質問への回答
すべて載っています。
やること:
- ダウンロードして印刷
- 担当者(自分)が一度、通読する
- わからない用語をメモ
完璧に理解しなくてOK。 まずは「こういうものか」と全体像をつかむ。
ステップ2:外注先リストアップ
自社の製造工程を紙に書き出しましょう。
書くべきこと:
- 原材料の仕入れ先
- 自社でやっている工程
- 外注している工程(どこに、何を)
- 製品の出荷先
例:
線材仕入れ(A商事)
↓
自社:切断・成形
↓
外注先B:熱処理
↓
外注先C:メッキ
↓
自社:検査・梱包
↓
出荷
このフロー図があるだけで、次のステップが見えてきます。
注意点:
- 外注先が他社製品も作っている場合、その旨もメモ
- 複数の外注先を使い分けている場合、すべてリスト化
ステップ3:前駆体(線材)サプライヤーへの依頼
前駆体(Precursor)とは?
製品を作るために投入される、CBAM対象の原材料のこと。
ねじ・ボルトの場合、線材が該当します。
やること:
線材の仕入れ先に、以下を依頼します:
「御社から購入している線材について、CBAM対応のために以下の情報を提供いただけますか?」
必要な情報:
- 線材1トンあたりのCO2排出量(特定内包排出量)
- その算定根拠
- データの対象期間
依頼のコツ:
❌ダメな例: 「CBAMの体化排出量データください」 → 専門用語すぎて伝わらない
⭕良い例: 「EUへの輸出のために、製品製造時のCO2排出量データが必要になりました。御社の線材1トンを製造する際に排出されるCO2の量を教えていただけますか?」 → 目的と必要な情報を具体的に
もしサプライヤーが対応できない場合:
総排出量の20%以内なら、デフォルト値を使えます。
ガイドラインの付属書に、線材のデフォルト値が載っています。
例:
- 鉄鋼の棒(熱間圧延):2.21トン-CO2/トン
- ステンレス鋼の棒:4.30トン-CO2/トン
ステップ4:自社の排出量データを集める
集めるデータ:
直接排出(Scope1)
- ガス、重油などの燃料使用量
- データ源:請求書、メーターの記録
間接排出(Scope2)
- 電力使用量
- データ源:電気代の明細
生産量
- 対象製品の年間生産量(トン)
- データ源:生産記録、出荷記録
期間:
- 原則として12か月間(暦年または会計年度)
- 季節変動を排除するため
データ収集のポイント:
- 完璧じゃなくてOK
- まずは「だいたいこれくらい」を把握
- 精度は後から上げていけばいい
ステップ5:外注先の排出量データを集める
これが一番大変です。
でも、避けては通れません。
外注先に依頼すること:
「弊社製品の製造を委託している工程について、CBAM対応のために以下のデータを提供いただけますか?」
必要なデータ:
- 対象工程での燃料使用量(ガス、重油など)
- 対象工程での電力使用量
- 弊社製品の製造にかかった時間または重量
外注先が複数の製品を作っている場合:
「弊社製品の製造時間は全体の何%ですか?」
この比率がわかれば、外注先全体の排出量を按分できます。
外注先が協力してくれない場合:
現実問題、すぐには対応できない外注先もあるでしょう。
その場合:
- まず、協力してくれる外注先のデータから始める
- 協力してくれない外注先は、推計値を使う(総排出量の20%以内)
- 段階的に精度を上げていく
ステップ6:計算する
集めたデータをもとに、計算します。
基本の式:
製品1トンあたりのCO2排出量
= (自社の排出量 + 外注先の排出量 + 線材の内包排出量)
÷ 製品の年間生産量
ガイドラインに載っている具体的な計算式に従って、一つずつ計算していきましょう。
計算のコツ:
- Excelで管理する
- 計算式をセルに入れておく
- 元データが変わっても、自動で再計算できるようにする
6. よくある質問(鉄鋼業界版)
Q1:「外注先が『うちは関係ない』と言って協力してくれません」
A:段階的にアプローチしましょう。
まず、なぜ必要なのかを丁寧に説明:
- EUへの輸出に必須
- データがないと取引を失う可能性がある
- 他社も同じことを求められている
それでもダメなら:
- 推計値を使う(総排出量の20%以内)
- または、他の外注先のデータで代用
- 将来的に精度を上げる方向で
Q2:「線材サプライヤーが大手で、中小の取引先にデータなんて出してくれません」
A:業界全体の動きを待つのも一つの手です。
大手の線材メーカーも、今後多くの取引先から同じ依頼を受けるはず。
そうなれば、標準的な体化排出量データを公表する可能性があります。
それまでの間は:
- デフォルト値を使う
- 業界団体(日本鉄鋼連盟など)の動向を注視
- 経産省の支援策を活用
Q3:「電力を再エネに切り替えても意味がないって本当?」
A:CBAM対策としては、現状では意味が薄いです。
鉄鋼製品の場合、Scope1(直接排出)のみが対象。
電力由来の排出(Scope2)は、移行期間中は報告のみで、課金対象外。
ただし:
- 将来的にScope2も対象になる可能性はある
- 脱炭素経営という観点では意味がある
- 他の環境規制への対応にもなる
だから、「無意味」ではないが、「CBAM対策の最優先事項」でもない。
Q4:「うちは直接EUに輸出してないから関係ない?」
A:取引先が輸出している可能性があります。
直接輸出していなくても:
- 取引先がEUに輸出
- その製品に自社部品が使われている
この場合、取引先から「CO2データください」と言われます。
だから、「今は関係ない」でも、準備は必要。
Q5:「2026年までに間に合わない気がします」
A:完璧を目指さなくてOKです。
移行期間中(2023年10月〜2025年12月)は、報告義務のみ。 課金が始まるのは2026年1月から。
そして、最初から100点を取る必要はありません。
優先順位:
- まず30点を取る(おおまかなデータ収集)
- 次に50点(主要製品の精密な算定)
- そして70点(全製品、全工程カバー)
2026年1月に30点でも、2027年に50点、2028年に70点でいい。
段階的に進めることが大事です。
Q6:「こんな複雑なこと、中小企業には無理では?」
A:一人で抱え込まないでください。
使える支援:
- 経産省のガイドライン(無料)
- 業界団体の支援策
- 地域の商工会議所
- 中小企業診断士などの専門家
そして、同じ悩みを持つ仲間がいます。
業界内で情報交換する、勉強会を開く、共同でコンサルを雇う。
そういった横のつながりが、今こそ大事です。
7. 今日からできるアクション
長い記事を読んでいただき、ありがとうございました。
最後に、今日からできることをまとめます。
今日やること(30分)
□ 経産省のガイドラインをダウンロード こちらから
□ 自社の製造フロー図を紙に書く
- 原材料の仕入れ先
- 自社工程
- 外注先
- 製品
□ 担当者を決める
今週やること(2〜3時間)
□ ガイドラインを一度、通読する
□ 外注先リストを作る
- 会社名
- 担当工程
- 連絡先
□ 線材サプライヤーに問い合わせメールを送る
- 「CBAM対応で、線材の体化排出量データが必要です」
- 「提供可能かどうか、まず教えてください」
今月やること(5〜10時間)
□ 自社の排出量データを集め始める
- 電気代の明細を1年分集める
- ガス・燃料の使用量を確認
□ 外注先に説明の連絡を入れる
- まず、「なぜ必要か」を丁寧に説明
- 協力をお願い
□ 簡易計算をしてみる
- デフォルト値を使ってもいいから、まず計算してみる
- 「だいたいこれくらい」を把握
3か月後の目標
□ 主要製品1品目の体化排出量を算出
- 精度30点でいいから、計算完了
□ 外注先の一部からデータ入手
- すべてじゃなくていい
- まず、協力的な外注先から
□ 社内に状況を共有
- 経営層に進捗報告
- 現場に協力を依頼
まとめ:鉄鋼業界のCBAM対応は「段階的に、仲間と」
鉄鋼業界、特にねじ・ボルト製造の中小企業にとって、CBAMは確かに大きな負担です。
でも、一人で完璧にやる必要はありません。
- 経産省のガイドラインを使う
- 業界団体の支援を受ける
- 同業者と情報交換する
- 段階的に精度を上げる
これが、中小企業の現実的な対応策です。
「2026年は遠い未来」ではありません。 あと数ヶ月ちょっとです。
でも、焦る必要もありません。 今日から、できることから、少しずつ。
それが、この記事の一貫したメッセージです。
※この記事は、経済産業省のガイドライン、ジェトロのレポート、日本鉄鋼連盟の公表資料などを参考に作成しています。最新の情報は、各機関の公式サイトでご確認ください。
※「ここが違う」「こういう視点も必要」というご意見があれば、ぜひ教えてください。一緒に、より良い情報を作っていきたいと思っています。




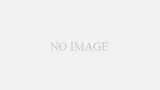
コメント